|
●「江戸の特産品開発 本草学と博物学の本」年表
|

『十品考』より鳳梨
『人參譜』 田村藍水(たむら らんすい)原著 4巻 2冊 写本
写真を見る 表紙 御種人参 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
序文も跋文もない本で、合計67種の人参を図入りで説明している。「目録」として人参が4つのグループに分けられ、「巻之一 真参部 十五種」「巻之二 假参部 十一種」「巻之三 冒参部 五種」「巻之四 俗参部 三十六種」とされている。67種の人参の中に「百済参」「新羅参」という名称はあるが、「朝鮮人参」という名称は出ていない。清水藤太郎著『日本薬学史』(南山堂)によれば、この『人參譜』は元文2年(1737)の著作である。 全国に採薬使を送った徳川吉宗(1684―1751)は人参の国産化も目標のひとつとし、対馬の宗家が朝鮮から秘密裏に手に入れた人参の種を各大名へ分け、(御種人参と呼ばれる所以)その栽培を目指していた。著者の田村藍水は、元文2年 (1737) 幕府から「朝鮮人参」を与えられて試作し、種を採ることに成功(藍水19歳)。その後、結実した種子を全国に広めたという。寛延元年 (1748)には、その成果をまとめた『人参耕作記』序刊 1冊を出している(藍水30歳)。種子が採れた後もさらに実用への研究を続けていたのであろう、さらに後の明和4年(1767)『参製秘録(さんせいひろく)』という本も撰していて、朝鮮人参の加工技術を詳細に述べている。 田村藍水(1718~1776)は、またの名を 坂上登(さかのうえのぼり)、元雄(げんゆう)、玄台ともいう本草家。江戸における博物誌の流れは、この藍水に始まるとも言われる人で、弟子の平賀源内とともに、日本初の薬品会を宝暦7年 (1757) に江戸湯島で開催した(藍水39歳)。 町医であったが、宝暦13年(1763)からは幕府に仕えたという。大坂の酒屋で、本草学や博物学のサロンの主であった木村蒹葭堂(1736―1802)とも交流があり(藍水より18歳年下)、本草学・博物学は江戸、長崎、大坂、名古屋をはじめとして日本全国へとネットワークを広げていこうとしていた。薬品会もまた、各地で開催されるようになり、そのネットワークづくりの好機となっていった。長男は善之 (よしゆき) (西湖) 、次男は栗本丹洲で、ともに幕医で博物家としても活躍している。善之は『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』という薬品会の出品物に対して書かれた物産解説書の校正に関わるなどしている。
|
『佐州産物志』 上・中・下
写真を見る 表紙 植物(モザエムナ) (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
この本はフランク・ホーレーの「寶玲文庫」の蔵書印を持っている。上巻には、細い筆で丁寧に産物の品名のみが書き連ねられているが、中巻と下巻には多くの絵が描かれている。中巻には植物17、きのこ1、海草など海辺のもの11の絵がある。また下巻には虫、貝、蛇、魚、海豚など17の絵がある。 上巻の最初は「穀類」の「粳米(うるちまい)」で始まる。「粳米」の中に29の名前があがっている。やはり米作りを長く続けた国民ゆえに、小さな違いも見逃さずに別々の名前をつけていったのであろう。日本人の米に対する細やかさを感じる。「粳米」の次には「早稲」として9種。「糯(もちごめ)」として22種の名があり、「粟」、「稗」、「黍」、「大豆」、「赤小豆」、「紅豆」、「緑豆」とそれぞれに数種の穀物の名が続いてやっと「菜類」になる。 さすが佐渡の産物誌、と感心させられるのは「金石」の項目で、「金銀石種類多シ」とあり、38もの金石の名前が挙げられている。
中巻・下巻の絵の説明には多くのものに「賤民採テ菜トス」とか、「賤民採テ糧食トス」とあって、庶民の食していたものだとわかる。 上巻の最後には「寛延二己巳年 秋 佐州相川御陣屋写之者也」と記されている。寛延2年は1750年である。八代将軍吉宗に信頼されて採薬使として全国を旅したという植村政勝は享保5年(1720)から宝暦3年(1753)までの採薬使の仕事を『植村政勝薬草御用書留』という書物にまとめているが、その34年の旅の終わる頃、この『佐州産物志』は書写されていることになる。ひとつのアイデアが人を動かし、日本の全国に広がっていったのと、ひとりの人間が大きなまとまりのある仕事を成し遂げるのとが、同時に行われていったように感じられる。植村の本は明治になってからも写されている。 |
『薩州産物録』 完 勝成裕 述
写真を見る 扉 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
著者の勝成裕は佐藤成裕( さとうせいゆう) (1762~1848) の名で有名である。佐藤成裕は江戸生まれの本草家で、号は中陵・温故斎・菁莪堂。薩摩・米沢・会津・備中松山の各藩に行き、それぞれ数年を過ごし、寛政11年 (1799) 以後は水戸藩に仕えたという(藩医だったらしい)。著作は非常に多く、ここにご紹介している『薩州産物録』の他、『飼籠鳥』(かいこどり)、や随筆の『中陵漫録』がよく知られている。 このうち『飼籠鳥』(かいこどり)は全20巻、416品の鳥について述べている本で文化5年の序文をもつ。また『中陵漫録』は「玉藻前、白狐、殺生石」という怪異譚が収められた本である。この他にも『鼠族図譜(そぞくずふ)』1冊という動物に関する本や『黴瘡秘録薬名考』1冊(寛政7年序)という薬品に関する本まで書いており、成裕の守備範囲の広さに驚かされる。 この『薩州産物録』では、産物が商品としてどのような評価を受けているのかについて、上品、下品などのランクづけをしており、他の産物誌に比べてより実践的な書の印象を受ける。たとえば、「蘇鉄」について、 そうしたするどい眼識を持つ人の著作だからという理由もあろうが、この本を読むと、薩摩という国は本当に貿易のうまみを堪能していたのだとわかる。自然の違いを大いに利用し、また中国、琉球からもたらされる産物を大消費地の大阪や江戸に運び、大きく儲けていたように受け取れる。 また、本の最後には「寛政四年壬子春日」の日付で国というものがどのようにして国益を守っていくのかということが9ページにわたって書かれている。経営の上手な薩摩を例にして、殖産興業が説かれている。この寛政4年には成裕は30台の青年であるが、その理想が語られている。少し引用して、この項を終わる。
|
『採薬録』 佐藤成裕 著 寛政7年写
写真を見る 序文 植物(丹参) (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
原著は佐藤成裕(勝成裕)。巻頭には「會津 楊皐山人兒島? 撰」(寛政7年7月)、「米澤 提學 片山剛」(寛政6年9月)、「佐倉隠醫 鶴甫謹書 干東都楓川」(寛政6年2月)と署名のある3つの序文がつけられている。原著者の佐藤成裕( さとうせいゆう) (1762―1848)は『薩州産物録』のところでも触れたとおり、江戸生まれの本草家で、号に中陵・温故斎・菁莪堂がある。薩摩・米沢・会津・備中松山の各藩に行き、それぞれ数年を過ごし、寛政11年 (1799) 以後は水戸藩に仕えたという(藩医だったらしい)人物である。この本の序文を書いているのも会津と米沢の人であるから、確かに佐藤成裕がかの地に行き、交流があったことの証にもなるだろう。 三番目の序文を書いているのは千葉の佐倉の医師であるが、今回、江戸時代の本草学や園芸に関することを調べていて、たびたび千葉という土地が関わっていることを知ることになった。『探索培養考編集』を著した菖翁(松平定朝)も、房総半島の東南部にある安房國朝夷郡・長狭郡内2,000石を継承する人であり、単に趣味として植物研究をしたのではなく、自国の経営という観点から園芸を見ていたのではないだろうか。大消費地である東京の近くにあり、黒潮の影響で気候温暖な千葉は今でも花づくりの盛んな地域である。 また、千葉県船橋市にある薬園台(現在は薬円台)の地名の由来はその名の通り、江戸時代に小石川(養生所)の薬草園である「下総薬園」がこの地に作られた事に由来している。この薬草園は、吉宗の命を受けた幕府御医師並の丹羽正伯と、日本橋の薬種商である桐山太右衛門によって設立され、朝鮮人参などの漢方薬の栽培が行われていた。丹羽正伯は三重県松阪市生まれで、本草学を京都の稲生若水に学んだ医師である。吉宗のもとで、日本全国の産物誌を作らせようと企画したのはこの丹羽正伯であったと言われる。しかし、宝暦6年(1756)に正伯が亡くなった後の下総薬園は、経営もうまくゆかず、消滅していったらしいし、また集められたはずの日本全国の産物誌もまとまった形では残っていない。しかしながら、採薬使たちが調べた各藩の産物は、明治になっても、また現代でも貴重な資料として利用されており、正伯の業績は無駄ではなかった。
|
『加賀国物産書』 上・下巻 享保20年 (文化8年書写)
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
跋を見ると「右 文化八辛未年 十月 前田士佐守直方賢候ヨリ借用写之者也 村井長世」とあり、享保20年(1736)幕府へ提出した物産書上帳を文化8年(1811)になって写した本であることがわかる。村井長世がどのような人物なのか、どういう理由があってこの本を写したかについては、何も記されていない。75年も前の物産書を何に役立てようとしていたのだろうか。 村井長世の名は石川県の江戸時代の人物としてインターネットで検索できた。加賀藩家老で、村井家の「家系図」や「村井家譜」の編集人として名を残している。また号を屋漏堂としていたが、その名がつけられた『屋漏堂禽譜』という鳥の図鑑のような書物は彼の編集によったとみられている。名古屋大学附属図書館・付属図書館研究開発室のホームページによると、幕末から明治にかけて日本の本草学を西洋に通じる植物学、博物学へと導いた伊藤圭介の『錦?禽譜』という書は、この『屋漏堂禽譜』という書物から70点もの図と文を引いているそうである。まさに、採薬使らの調査研究が近代日本の科学へとつながる、という話に合致している。 上巻には68葉があるが、その36枚目までが米で占められている。「穀部」は粳米の早稲、なかて、晩生、もち米の早稲、なかて、晩生とあり、その後、粟、もち粟、稗、黍、大麦、小麦、そば、大豆、小豆、ささげ、豆とあって上巻を終わる。穀物とひと口に言っても実に多様で、ある意味では豊かさを感じさせる。同じ地方でも田畑のある場所によったり、村によったりで別の品種を植えていたのだろうか。現在のような種苗の流通状況とはちがう江戸時代のことである。 書写している字は跋にある村井長世の字とは異なり、線の細い女性の字に見える。丁寧な変体仮名で綴ってある。細い筆の跡からは、器用ではないが真面目で従順な印象を受ける。村井の娘か、若い妻ででもあったろうか。 この書も「寶玲文庫」の朱印と「慶応義塾図書館」の朱印があり、表紙にはペンの交差した慶応マークのラベルシールが貼り付けてある。 |
『草木育種(そうもくそだてぐさ)』 上下2冊 岩崎常正(灌園)
文化15年戊寅(1818) 江戸・千鍾房・玉山堂合刻
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
岩崎灌園の編成した園芸書。陰陽道の占いのように、「耕作田吉日」として、干支で良い日をあげたり、神農が甲寅の日に亡くなったのでこの日は開田には良くないなどと述べていたりするかと思うと、実践的に土質・水利・種蒔き・施肥・接ぎ木・挿し木・移植などの仕方を説明してもいる。『本草』『花鏡』や中国の種樹書、仏典なども引用している。 たくさんの花を育てた灌園の著作だけに、もちろん経験を活かして書かれていると思われる。その記述はとても詳細で、たとえば肥料のところでは、牛糞は桃を植える時牛屎に土をまぜ埋め置いて使うと良い、とか羊の屎は立夏の前に泥に合わせ蓮を植えると花が多くなる、などと書いてある。接木の説明をするところでは枝の切り方や株と枝の縛り方などが、わかりやすい絵で説明されている。「常正自画」とあるから、灌園自身の作画なのだろう。 一方では、中国の高雅な文化として園芸がとらえられてもいた。各藩は「お留め花」という門外不出の観賞用植物を育て、将軍への献上品などにして、その園芸の腕を競っていた。牡丹、芍藥、菊、蓮、芙蓉、蘭といった中国で人気のあった花に加えて桜、躑躅(つつじ)、椿、杜若、松本仙翁、撫子、桜草、楓、万年青(おもと)、石斛(せっこく)なども盛んに栽培育種されたらしい。桜草や花昌蒲、朝顔などでは「花連」という結社までが作られ、厳しい入門の資格審査を受けたのち、家元制度のようにして初伝、中伝、奥伝、皆伝と進めて育て方の伝授が行われるという閉鎖的な活動もあった。 庶民にとっても花は身近な存在で、飛鳥山の桜、亀戸の藤、堀切の菖蒲など花見の名所もできて、寺社などさまざまな場所で品評会や植木市というものも多く開催されたようである。書籍の世界でも、蘭や万年青の番付をしたものが見られるが、注目される植物の新しい品種を作りたい、育てたいという願いは身分に関わりなくあったであろうから、この『草木育種』も広く読まれたのではなかろうか。 |
『本草図譜』 岩崎常正(灌園)著 文政11年(1828)
写真を見る 表紙 大正版表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
江戸時代、江戸城や将軍の護衛を行う下級武士、つまり騎乗が許可されない武士である御徒(徒士 かち)が多く住んでいたことから今もその名の残る御徒町に、岩崎灌園(1786~1842)は住んでいた。徒侍であった彼は、自宅の庭に植物を植えて育て、それでも足らずに後楽園の近くに土地を借り受けて栽培をしていたという。 この『本草図譜』は岩崎灌園が写生した図に簡潔な解説が付けられているもので、彩色がとても美しい。野生種のみでなく園芸品種をも含んだ植物(岩石、動物も収載)約2,000種が掲載される95巻*、92冊の大部の図鑑である(当館は巻37~48までを所蔵)。そのほとんどが著者の自園で鉢植えされていたものと言われ、20余年の歳月を費やし文政11年(1828)に完成させている。
*96巻としている資料もあります。 |
『梅品真図説』 弘化3年(1846)書写
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
佐村八郎『国書解題』には「梅の種類凡て80種を列挙し、一々着色図に作りて、悉く説を附載す。」とある。 80種の梅の花は美しい絵で表され、二、三行の説明文が付けられている。たとえば2番目に紹介されている「冬梅」の説明文には 冬梅 江陰縣志 とあり、白い梅の花と緑の実をつけた絵を載せている。花の様子やどこに咲く花なのかを伝えているので、好きな者であったら、訪ねてみたくなるだろう。 本の前半の8葉と後半の10葉は和文で書かれ、上のような説明文がついているが、中間の20葉は漢文で書かれ、どこに咲いているかなどの説明はない。こうした部分は中国の書からの引用なのだろうか。 それにしても、江戸時代の園芸は驚くほど進んでいた。現代日本ではバラや蘭、あるいは皐月など特定の植物を楽しむための園芸の本が多数出版されているが、江戸の人達もこのようなぜいたくな本を作って同好の人々と花を楽しんでいたのである。 巻頭の文章の最後の部分に「清人潘穉峯百梅の詩あり これにより彼によりてここに図譜を作り草稿の間々同好の友に贈のみ 梅秀外史寫真」とある。『百花詩図考』で出てきた清人・潘穉峯の名がまたここでも見える。植物の絵のそばに気の利いた文章を添えられる彼は、売れっ子の詩人かコピーライターであったのだろうか。
|
『探索培養考編集』 菖翁 撰 新遠重遠 写
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
著者の菖翁は伊予松山藩松平氏(隠岐守家)の分家、松平織部家第7代の松平定朝(まつだいらさだとも)のことである。定朝は6代松平織部定寅公の長男として安永3年(1774)に誕生、11代将軍・家斉の頃初登城し、父亡き後、安房國朝夷郡・長狭郡内2,000石を継承する。文政5年(1822)禁裏附となり、江戸を離れ京都へ赴任。父の影響を受け幼少の頃から親しんだ趣味の花菖蒲栽培を京都でも続け、優秀で美しい花を仁孝天皇へ献上し、御礼のお言葉を賜ったという。 今で言えばいわゆるグリーンフィンガーらしく、百種の花について、植物の育て方のポイントが書き連ねてある。絵はない。内容を読むと、たとえば芍藥の項には、芍藥は鉄刀を嫌うので、真鍮刀を使うように、と書いてある。また、蓮の項では植え替えにちょうどよいのは浮き葉2、3枚の時とし、植え替えに良い時期やその方法について述べ、豆腐のおからを土に混ぜるとか、水は翌日に差すなどの指示をしている。さらに、蕾のある時に運送すると弱って開花しなくなる、などと育てる時の注意が事細かになされている。 百種に選ばれた花は今日の園芸界でも人気のものが多いようで、種々の蘭や熊谷草、大文字草、化倫(エビネ)など、玄人好みのものが目立つ気がする。また、「5 ヲキサアリトス ロヲザアー」「6 レリイナルキス」「7 ビッキ」「68 フラストハットス」「92 コロイチルウルメイニート」「97 ダリアス」と、カタカナ標記の植物が6つ入っている。「97 ダリアス」という名であがっているのはダリアのことだろうと思われるが、これには「方言 ハルシヤ菊」と書かれ、下品の草とされている。百種にこだわってこの本をまとめたものの、すべてが上品の花を選ぶというのも難しかったのだろうか。 江戸麻布桜田町(現在の港区元麻布 六本木ヒルズの裏手辺り)に、約2,500坪の旗本屋敷を持ち、ここで60年以上にわたり花菖蒲の改良を重ねた定朝が生涯で作り出した花菖蒲は約300種で、これらのうち約20種が今日に残されているという。菖翁の名のとおりの人生であったらしい。花菖蒲の改良をすすめる中、栽培法を著し、『花菖培養録』(嘉永年間)(初題『花鏡』弘化4年)と『百花培養集』
(初題『百花培養考』)を著している。彼は、こうした本を毎年改訂していたそうで、展示品の『探索培養考編集』も『百花培養集』を正式に出す前の状態のものを写した本かもしれない。『探索培養考編集』の跋には弘化3年とあるので、原著は最初の頃の稿本だった可能性もあると思う。 |
『拾品考 第一 附図』 野田青葭 著 石崎融齋 絵
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
野田青葭という人物が長崎に入ってきた海外の植物10種について書いた本で、石崎融齋が絵を描いている。舶来薬種商である著者が、偶然手に入れた植物を育てたり、扱っている薬種の中から種子を撒いて育てたりして知った珍しい植物について語っている。文章は漢字カタカナ混じりのものであるが、せっかく育てた植物を「僕奴」が雑草と思って抜いてしまい、なんとか助けようとしたが「日々凋萎」してついに根が腐り、人が死んだときのように悲しい思いをした、とあったり、たくさんの花をつけた植物を見て、「余ガ歓喜、挙ゲテ言ベケンヤ」と大喜びするさまを描写したりしていて、非常に温かみが感じられる文章である。 絵を描いたのは「長崎画史賞鑑家」(跋にあるママ)という肩書きの石崎融齋という人物であるが、この人の名前は長崎市脇岬にある観音寺の天井絵(長崎県指定有形文化財・絵画)の製作者とみられる人物名と同じで、長崎地方のこの時代に絵画の腕を知られた人だったとわかる。観音寺の天井の板1枚には「長崎画史鑑賞家七十九翁、禁衣画師石崎融思 内容は、藤蔓生相思子、鳳梨、金毛狗背、番海芋、多麻林度、丁香樹、肉豆?樹、蠻山山慈姑、大葉旃那、紅豆樹という10種の植物が取り上げられている。目次には、「次編目録」として、別の10の植物の名が書かれている。著者は10種ずつ取り上げて、シリーズものを目指していたのかもしれない。 この刊本には大阪心斎橋通の浅井龍草堂、河内屋吉兵衛製本記という判が押してある。薬種商の集まっている大阪で発行された本のようだが、本文中には長崎のオランダ館のオランダ人医師に話を聞いたりしているようだから、青葭という人は大阪と長崎を行ったり来たりしていたのであろうか。その他にも李時珍(1518―1593)の『本草綱目』や『廣東新語』、『秘傳花鏡』などさまざまな書物も引いており、華人の話なども載せる。野田青葭はとても研究熱心で知識欲旺盛な人であったにちがいない。
|
『嘗草』 大正13年創刊 右左見直八、梅村甚太郎、鈴木釘次郎、他
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
大正13年9月15日に創刊された、名古屋の本草学のグループの会報兼雑誌である。創刊号の最初に『嘗草』という名は古代、大巳貴命(おおなむちのみこと)が蒲の穂を以て創痍を治した兎の発明を観て草木の薬効を知り、また中国の炎帝神農が百草を嘗めて薬効を知ったという和漢の故事にちなんでつけたと述べられている。青い表紙には『嘗草』と横書きの雑誌名があり、「國譯本草綱目」と縦書きで入っている。そうして古代の装束をつけ、みずらを結った大巳貴命が蒲の水辺に立っている絵が描かれ、一番下には号数が記されている。 名古屋といえば、江戸の本草学の同好会「赭鞭 (しゃべん) 会」とともに有名な「嘗百 (しょうひゃく) 社」があったところで、伊藤圭介を輩出した土地でもある。もともと本草学の盛んなこの地で右左見直八、梅村甚太郎、鈴木釘次郎らがこうした会を立ち上げたのは当然のことであった。大正から昭和にかけたこの時期、周辺にも多くの研究会ができていたらしく、隣の三重県でも三重博物会のほかに、伊賀植物同好会・四日市植物同好会・中勢博物同好会、宇治山田理科学会・神都理科学会・尾鷲郷土博物同好会・熊野博物同好会などの多数の動植物等の研究会や同好会が発足し盛んな活動をしたということである。(参考:三重県史Q&A http://www.pref.mie.jp/BUNKA/TANBO/Q_A/ ) また、巻末にある「嘗草會の顧問及後援者」というところには |
『蒹葭堂遺物』原著 木村蒹葭堂 谷上隆介編
高島屋呉服店内 蒹葭堂会 発行 大正15年11月
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
木村蒹葭堂(1736―1802 世粛、巽斎、坪井屋(壺井屋)吉右衛門)は、大坂の酒屋の生まれ、商売は継がずに文人と交わり、多くの蔵書と博物学的なコレクションをしたユニークな人物である。この本は、その木村蒹葭堂125 年忌を記念して400 部限定で発行された復刻版である。 1.禽譜 2.奇貝図譜 3.ウェインマン氏植物図 という3冊で、原著は彩色されたものであるが、この復刻版は単色刷りである。大阪府立図書館初代館長の今井貫一、画家の菅楯彦が大阪町人の先学、蒹葭堂を祭祀しその遺芳を表彰することを提唱したところ、高島屋も賛同し、浪華の名士たちの熱誠なる賛助を得て成った復刻事業であった。 「1.禽譜」は鳥の図鑑である。序文は鷹司信輔(たかつかさ のぶすけ 1889―1959)が書いており、図譜は「其精巧緻密實に空前の逸品なり」と褒め称えている。ちなみに、鷹司信輔は公爵で貴族院議員や明治神宮宮司を勤めた鳥類学者。日本鳥学会の創立に関わり会長ともなった「鳥の公爵」と呼ばれた人である。この「1.禽譜」の原著は富岡鉄斎が所蔵していたもので、冊子の巻頭には富岡鉄斎の箱書きの写真があり、蒹葭堂の号の由来は井戸を穿って葦が生えてきたことからつけたこと、また、蒹葭堂が商売上のことで罪を得て一時伊勢長島に移り住んだことなどが書かれている。 「2.奇貝図譜」には岩川友太郎が序文を寄せている。岩川友太郎(1855-1933)は大森貝塚を調査したアメリカ人、モース(腕足類研究家)に直接教えを受けた東京大学理学部生物学科の第一回卒業生(1881年)で、日本最初の生物学英和対訳辞典『生物学語彙』(1884年)を著した学者である。病を得てこの「2.奇貝図譜」を詳細に研究できないことを残念に思っている、としているが「2.奇貝図譜」と、この序文の書かれた大正15年の時点での貝の名称の違いについて、細かに列挙して示している。また、「無名貝」とされている貝について、「これは世界的に有名な「オキナエビス」一名「長者介」と称せられて居るもの」と延べ、英国博物館から依頼があったものを東大三浦三崎実験所の青木熊吉氏が見つけ、箕作博士にご褒美として大金をいただいたことから付けられた名であると明かしている。 「3.ウェインマン氏の植物図」の冊子に序文を載せているのは、『本草図譜』の大正版に「本草図譜名疏」をつけた白井光太郎である。『本草図譜』(大正版)もこの『蒹葭堂遺物』も大正15年に出ているから、この前後、白井は大いに復刻事業に取り組んだことになる。 3冊ともに各分野で研究を続けてきた人によって序文が書かれているが、江戸時代の人々の好奇心が大正時代にまで伝わり、さらに発展しているということが感じられる。 |
『土州測岳志産物編』
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
土州は土佐のことで、今の高知県である。その土佐の67の物品をあげて、その産地や特徴、また言い伝えなどを書いている。縦罫の原稿箋に丁寧に書写されている。24葉。毎半葉10行。毎行19文字。 下に、取り上げられているものを表にした。すでに産物として有名になっているものもあるが、まだ使い道の決まっていないものもある。字消石など、何かに使えそうだが、商品化には至っていないようだ。 |
『越信土産』 全
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
これも「寶玲文庫」の印が押された本である。越後と信州の産物を絵入りでまとめてある。「石品」に22項目、31種、「草木」の分野に22項目23種が載せられている。 他の産物誌に比べ、鉱物類の割合が多いのが特徴だが、石の絵にも丁寧に色がつけられ、中には雲母まで使って、その様子をなんとか伝えようと努力している。「木葉石」が複数描かれていたり、会津の人が蔵していた「菊葉石」という蝦夷産の石を載せてしまっていたりするところを見ると、この本の作者は産物をまとめる、というよりは珍しい石について調べたかったのではないかと考えたくなる。「星ノ糞石」は真っ黒な石が描かれているが、隕石の類であったのだろうか。また、「越後産・未詳」とされる黒いブラシのような絵は恐竜のデンタルバッテリー(歯)のようにも見えるが、いったい何なのだろうか。 「草木」の項の絵にも彩色がされているが、あまり上手ではない。また、解説も植物の外見について述べるだけの項目が多く、詳しくはない。各地に派遣された採薬使やその手伝いを命じられた者の手になるきちんとした本ではなく、越後、信州を旅して回った者が目についたものを、自分の興味の範囲でまとめた書物ではなかろうか。書名についた「土産」という言葉もそのような事情を表しているように思える。 しかし、この時代の文人たちには珍しい石をコレクションすることは間々あったことらしく、『木村蒹葭堂のサロン』(中村真一郎・著 新潮社2000年)の中にも、駕篭に乗っていて途中で石を拾って持っていたら、駕篭かきが料金の値上げを話し合っていた、というエピソードが語られている。まずは、このような素人の物好きがあり、それが積み重なって明治時代の科学が始まったことを考えれば、この『越信土産』の石の絵も貴重なものとしなければならない。 |
『百花詩図考』 5冊
写真を見る 表紙 (ご覧の後は、ブラウザのボタンでお戻りください) 年表へ戻る
|
研医会のホームページでおなじみの美しい植物画の本。巻一の最初には「清人潘穉峯 原本 百花詩圖考 呉門寶翰樓○」とある。(○部分は欠損)また、巻二、巻四、巻五の最初には「雲間潘鐘﨑*穉峯録 男淑伽樹宏編次(* つくりは培という字に同じ)」とある。 漢文と絵とが一対になっており、文は七言絶句のようだが、説明調で韻をふんでいないこともある。序文には詠とあるので、主旨としては詩を楽しむ本なのであろう。絵は彩色がとても美しく、丁寧に描かれたものである。四周の茶色の界線の中にうまくおさまるように、形よくそれぞれの植物が描かれている。 巻一の最初は風蘭(フウラン・富貴蘭とも表記する)で始まっている。この花は将軍、大名、旗本などの高位のものが愛好した花として知られている。花だけでなく、葉や気根も鑑賞の対象となっていたらしく、この輸入元である中国にはない鑑賞法は日本独特の観葉植物の育種へとつながっていったと思われる。だが、この『百花詩圖考』には赤い葉の植物がいくつか載せられてはいるが、ほとんどは花の咲いた状態の絵で占められている。 描かれている植物には蘭の類が一番多い。現代日本でも毎年「世界らん展」のようなイベントが行われていて、人気の高い花であるが、清代の中国人も、江戸の人も、この花が好きだったことがわかる。蘭以外の植物も花の咲いている状態を絵にしてあるが、中には実のついた状態のものも含まれている。また、同じ種類や近い種類の植物が数ページにわたり並べられていることはあるが、巻ごとに春夏秋冬の季節にそって植物が整理されているわけではない。植物の分類よりは、詩と絵を楽しむ冊子のようである。 中村真一郎の著作『木村蒹葭堂のサロン』(2000年 新潮社)の一節に、蒹葭堂は「貝の標本などは、かなり近代科学的に整理した物を作りながら、一方で自然現象に対してディレッタント(ものずき)的好奇心による、知識の不整合もあり、これが多くの物好きな素人を、好学の専門家と共に彼のサロンに引き寄せた、…」という文章があるのだが、江戸の博物学というものは、まさにそういった状況のものが多かったのではなかろうか。動物学にしても植物学にしても、鉱物学にしても、まずは好奇心があり交流を始め、それが分類されるようになって、科学へと進んでいく土台になっているようだ。そして、その素地として、中国から入っている本草学や漢詩の知識と技能がそうした人々の交流をつないでいたように思われる。『百花詩図考』もまた、そうした人々の交流の中に生まれた書籍であったにちがいない。 |
|
フランク・ホーレーの寶玲文庫
|
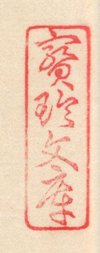 |
研医会図書館